国民健康保険案内
国民健康保険の概要
国民健康保険は、病気やケガに備え、加入者がお金(保険税)を出し合い医療費の支払いにあてる助け合いの制度です。日ごろから一定の保険税をかけておき、万一の病気やケガのとき安心して十分な診療が受けられるようお互いが助け合っていく制度です。
国民健康保険も他の社会保険制度と同様に次のような方を除き、全ての方が加入者(被保険者)となります。
(注意)国民健康保険では、大人や子どもの区別無く一人ひとりが被保険者ですが、加入は世帯ごとで行います。
国民健康保険に加入できない方
- 会社の健康保険、船員保険、各種共済組合などの社会保険各法の被保険者(組合員)と被扶養者。
- 生活保護を受けている方。
こんなときには届出を
次の場合は、14日以内に健康保険課保険年金係へ届けてください。
(注意)加入の届け出が遅れると保険税は遡ってかかります。
加入しなければならないとき
- 町外からの転入
- 職場の保険がきれたとき
- 子供が生まれたとき
- 生活保護を受けなくなったときなど
加入の必要がなくなるとき
- 町外への転出
- 職場の保険に加入したとき
- 死亡したとき
- 生活保護を受けるようになったときなど
変更が生じたとき
- 町内で住所を変えたとき
- 世帯を分けたり一緒になったとき
- 世帯主や氏名が変わったとき
- 修学のため、家族が町外へ転出したとき(在学証明書等が必要)など
高額療養費の給付
1カ月に支払った医療費の一部負担金が一定額を超えたときは、超えた分が「高額療養費」として支給されます。限度額は70歳未満の方と70歳以上75歳未満の方では異なり、所得区分によっても異なります(下記表参照)。
◆70歳未満の方の自己負担限度額(月額)
| 区分 | 年間所得※1 | 限度額(3回まで) | 限度額(4回目以降)※2 |
| ア | 901万円超 | 252,600円+ (医療費の総額-842,000円)×1% |
140,100円 |
| イ | 600万円超 901万円以下 |
167,400円+ (医療費の総額-558,000円)×1% |
93,000円 |
| ウ | 210万円超 600万円以下 |
80,100円+ (医療費の総額-267,000円)×1% |
44,400円 |
| エ | 210万円以下 | 57,600円 | 44,400円 |
| オ | 住民税 非課税世帯 |
35,400円 | 24,600円 |
◆70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額(月額)
| 区分 | 外来(個人単位)の 限度額(A) |
外来+入院(世帯単位)の 限度額(B) |
||
|
現 |
3 | 課税所得 690万円以上※4 |
252,600円+ (医療費の総額-842,000円)×1% 【140,100円※2】 |
|
| 2 | 課税所得 380万円以上 690万円未満※4 |
167,400円+ (医療費の総額-558,000円)×1% 【93,000円※2】 |
||
| 1 | 課税所得 145万円以上 380万円未満※4 |
80,100円+ (医療費の総額-267,000円)×1% 【44,400円※2】 |
||
| 一般 | 18,000円 〈年間上限144,000円〉※7 |
57,600円 【44,400円※3】 |
||
| 低所得者2※5 | 8,000円 | 24,600円 | ||
| 低所得者1※6 | 8,000円 | 15,000円 | ||
※1 年間所得=総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額
※2 過去12ヶ月間で、同じ世帯での支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
※3 過去12ヶ月間に(B)の限度額を超えた支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
※4 同一世帯に一定の所得以上(住民税課税所得が145万円以上)の70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者がいる方。ただし、70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者の収入合計が、一定額未満(単身世帯の場合:年収383万円未満、2人以上の世帯の場合:年収520万円未満)である旨申請があった場合を除きます。
※5 住民税非課税の世帯で、低所得1に当てはまらない方。
※6 住民税非課税の世帯で、同じ世帯の各所得が、必要経費・控除(公的年金は控除額80万円)を差し引いたときに0円になる方。
※7 年間上限額は、8月から翌年7月までの累計額に対して適用されます。
★75歳到達月は、国保と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1になります。
限度額適用(標準負担額減額)認定証
医療費が高額になるときは、入院・外来どちらの場合でも「限度額適用(標準負担額減額)認定証」を提示することで、医療機関での窓口での支払いは限度額までに抑えることができます。あらかじめ健康保険課保険年金係または住民生活課砥用庁舎総合窓口係にて申請ください。
70歳以上の一般区分の方は発行が不要となります。
マイナ保険証を利用すれば、限度額適用(標準負担額減額)認定証の事前申請が不要となり、高額療養費制度における限度額を超える支払いは免除されますのでマイナ保検証をぜひご利用ください。
療養の給付
病気やケガのため、保険取り扱いの病院などで診療を受けた場合の患者負担額は2割または3割です(8割または7割は国民健康保険が負担しています)。
受診のときは保険証を必ず病院の窓口に提示してください。
療養費の支給
いったん全額を支払いますが、その後、国保の窓口へ申請し審査で決定すれば、自己負担分を除いた額が、あとで支給されます。
医師が必要と認めたコルセットなどの補装具代等があります。
申請に必要なもの…補装具を必要とした医師の証明書、領収書、保険証、印鑑、本人確認書類
その他の給付
その他、つぎのようなときに支給されます。
出産育児一時金
加入者が出産(妊娠85日以上の死産・流産を含む)したときに支給されます。
(申請に必要なもの…保険証、印鑑、領収書・明細書、医療機関等から交付される直接支払制度に係る代理契約に関する文書、本人確認書類)
葬祭費
加入者が死亡したとき、葬儀をおこなった人に支給されます。
(申請に必要なもの…保険証、印鑑、通帳の写し、本人確認書類)
入院時の食事代
入院時の食費はその他の医療費と別枠で、下表のとおり定額自己負担となっています。
| 区分 | 金額 |
|---|---|
|
一般(下記以外の人) |
1食510円 ※1 |
過去1年間の入院が90日以内 |
1食240円 |
過去1年間の入院が91日以上 |
1食190円 ※2 |
| 低所得者1 | 1食110円 |
(注意)マイナ保険証をお持ちでない方で住民税非課税世帯、低所得者2・1の方は「標準負担額減額認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となります。
※1 小児慢性特定疾病児童等または指定特定医療を受ける指定難病者は、300円の場合もあります。
※2 低所得者2に該当し、過去12ヶ月で入院数が90日(低所得2の区分の認定を受けている期間に限る)を超える場合は、健康保険課保険年金係または砥用庁舎総合窓口係で長期入院該当申請することで190円に減額されます。
保険税
加入人数とその前年の所得額等で決まり、納付額は世帯主に通知します。ただし1年間の保険税が確定するのは毎年6月になります。
保険税の納税義務者は世帯主になります。
交通事故などにあったら
被保険者が交通事故などによって、ケガをされたときは、世帯主はすみやかに、健康保険課保険年金係に届けてください。届け出がないと、保険診療ができませんのでご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康保険課
〈美里町役場 中央庁舎〉
〒861-4492 熊本県下益城郡美里町馬場1100番地
電話番号:0964-46-2113(直通)
お問い合わせはこちら












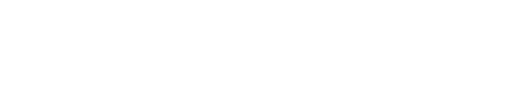

更新日:2025年04月01日