天然記念物
銀杏の木

[所在地:美里町甲佐平] [指定:昭和43年12月15日]
甲佐岳、福城寺は天台宗総本山比叡山延暦寺の末寺で、海抜753メートルの山容急峻な山腹に位置し、この境内にある。幹回り11メートルもあり、樹齢800〜1,000年と推定される。寺は、遠く嵯峨天皇の御代、弘仁2年(810年)頃、五穀豊穣及び世の安泰を祈願し再興されたと伝えられる。
槙の木
[所在地:美里町甲佐平] [指定:昭和43年12月15日]
甲佐岳、福城寺は天台宗総本山比叡山延暦寺の末寺で、海抜753メートルの山容急峻な山腹に位置し、この境内にある。
根周りの大きさは4メートルあり、木の高さは約20メートル。樹齢は不明だが、相当の年月をこの境内で過ごしてきたものと思われる。渦巻状の幹が見事である。
大杉
[所在地:美里町三和] [指定:昭和47年12月22日]
三和地区常海の入口にある。幹周り7.6メートル、高さ36メートルある。根から3メートルほどのところから多数の枝が出ている。樹齢は300年以上と推定される。古木にもかかわらず、幹の空洞もほとんどない。付近の人々は、この杉を「地の神さん」と呼んでいる。
いちい樫
[所在地:美里町豊富] [指定:昭和61年4月21日]
竹の迫神社境内にある。幹周り6.3メートル、高さ25メートルの古木で樹齢約1,000年と推定される。鳥居を入り石段を登る左手に、うっそうと生い茂り、歳月の経過を物語っている。
西山のつつじ(オンツツジ)
[所在地:美里町西山] [指定:昭和49年3月]
正法寺跡境内一画の小高い丘に群生している。高さは4〜5メートルに及び、毎年4月下旬から5月上旬の満開時には、丘全体をつつじが覆う。伝説によると、天文五(1740)年一月八日に逝去した正法寺の僧・鉄禅無味和尚の手により植樹されたものといわれている。
いや川水源の川ベニマダラ
[所在地:美里町中小路] [指定:昭和53年9月25日]
水源は鳳林山の麓に湧出しており、カワベニマダラとはこの川石に付着する紅苔の一種である。森通保博士の命名による。昔の人たちは、お産があるとそのいやをこの川で洗い清めたため、血が川の石に付着して紅くなったという。それより胞衣川(いやがわ)の名が生まれた。
白石野のいち樫
[所在地:美里町白石野] [指定:昭和49年3月]
幹回り6.8メートル、根回り10.6メートル、樹高26.0メートル。推定樹齢約800年。白石野公民館に隣接しており、根本には地蔵が祀られている。
吉見神社の公孫樹
[所在地:美里町小筵] [指定:昭和49年3月]
幹回り4.2メートル、樹高約20.0メートル。推定樹齢約300年。公孫樹としては美里町一の大木であり、熊本県緑化推進委員会により、明治百年記念樹にも指定されている。
慶専寺の藤
[所在地:美里町津留] [指定:平成6年4月1日]
房の長さ70〜100メートル、幹回り1.6メートル。推定樹齢約100年。慶専寺の入り口に所在し、丁重に管理されている。
この記事に関するお問い合わせ先
社会教育課
〈中央公民館〉
〒861-4406 熊本県下益城郡美里町馬場6番地
電話番号:0964-46-2038(直通)
お問い合わせはこちら












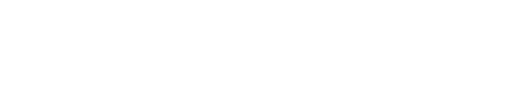

更新日:2024年03月01日