町の歴史
この地域では、古代には緑川沿いに集落があり農耕が営まれ、中世には阿蘇氏領や甲佐大明神の社領となり、その後近世に入り加藤氏領を経て細川氏領となっています。
その後、明治維新を経て、明治22年の町村施行の後、いわゆる「昭和の大合併」により、昭和30年1月1日に中山村と年祢村が合併して中央村となり、ついで昭和30年4月1日に砥用町と東砥用村が合併して砥用町が誕生しています。また、中央村は昭和50年に町制を施行し、中央町となっています。
なお、昭和30年7月10日に当時の中央村大字今、坂貫、下草野の3つの地区と大字岩野の一部が砥用町に境界変更され、その後下草野の区域は昭和32年7月1日に境界変更により中央村に復帰しています。
中央町は、昭和30年の合併以降、企業誘致や小中学校の統廃合、日本一の石段建設、カントリーパークの整備、基幹産業である農業の振興等に取り組んできました。一方砥用町も、企業誘致や小中学校の統廃合、緑川ダムや霊台橋を中心とした観光整備、簡易水道の整備、基幹産業である農業の振興等に取り組んできました。
町名の由来は、中央町は熊本県のほぼ中央に位置していたことから、また砥用町は平安時代の書に「富神郷」と出ているのが始まりといわれ、「と」は山、「むち」は神の意味があり、山と神の又は山神の郷といういわれをもつと伝えられています。
平成16年11月1日に中央町と砥用町が合併して美里町が誕生しました。合併時の人口は12,849人、面積は144.03km2となっています。 美里町の町名は、全国から公募した中から選考し「いつまでも美しいふる里でありますように」等の理由から美里町となっています。
この記事に関するお問い合わせ先
総務課
〈美里町役場 中央庁舎〉
〒861-4492 熊本県下益城郡美里町馬場1100番地
電話番号:0964-46-2111(代表)
お問い合わせはこちら












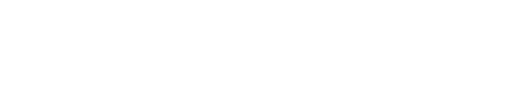

更新日:2024年03月01日